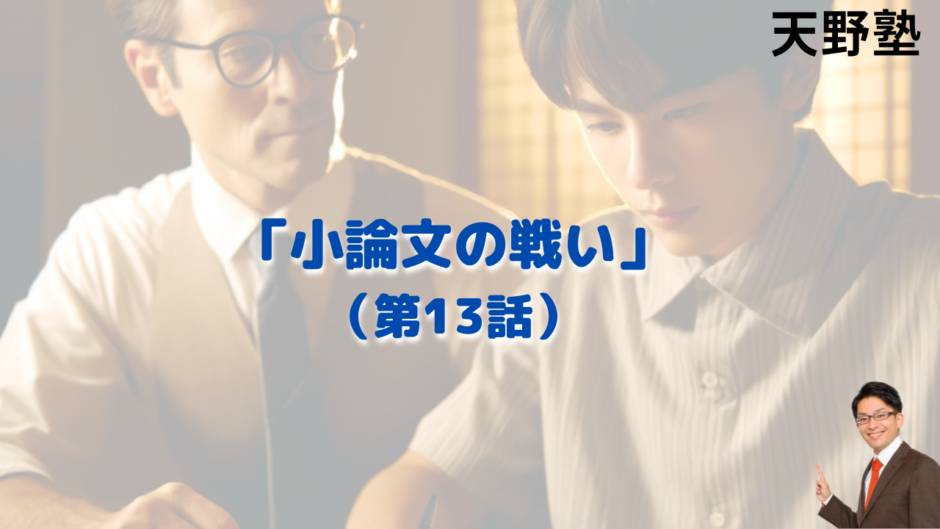~「考えて、書く。書いて、考える。」~
1. 初めての慶應小論文——2018年 環境情報学部の問題
「どの問題から始める?」
颯太くんにそう尋ねられたとき、私は慶應環境情報学部の2018年の小論文を選んだ。
理由は2つ。
✅ この問題は、小論文の知識がなくても取り組めるから
✅ アイデアと独特な物語の構成力があれば戦えるから
「この問題なら、颯太くんなら面白いものが書けるんじゃないかと思ってね。」
彼の性格はユニークで、自分なりの考えを持っている。
それなら、小論文の型に縛られるより、「自由な発想」を活かせる問題 からスタートするのがいい。
それに——
「慶應の小論文を1つでも書けた」という実体験が、次のステップにつながる と思ったからだ。
2. 「え、これなら書けるかも?」
問題を読んだ彼は、少し考えたあと——
「これなら、なんか書けそうな気がする。」
と、意外なほど前向きな反応を見せた。
今までの「小論文って何を書けばいいの?」という態度とは明らかに違う。
「じゃあ、まずは書いてみよう!」
「おう。」
3. 颯太くんの独特なストーリー構成
彼はペンを走らせ始めた。
普通の受験生なら、「論理的に正しいか?」を気にしながら慎重に進めるかもしれない。
しかし、颯太くんは違った。
✅ ストーリー性のある独特な展開
✅ 序盤から読み手を引き込む構成
✅ オチがついているユニークな締め方
「おもしろい。」
私は、彼の文章を読んでそう感じた。
「どう?」
「いや、これはこれでアリだと思うよ!」
「マジ?」
「うん。ただ、これを小論文として仕上げるために、もう少し『論理のつながり』を意識するともっと良くなる。」
「ふむ。」
彼は納得した様子だった。
4. 「書けた!」という実体験が大きな一歩
彼が書いたものは、厳密には「小論文」ではなく、「物語寄りの文章」だった。
しかし、それでも 「とにかく書けた」 ということが重要だった。
✅ 「慶應の小論文を書いた」という実体験が自信につながる
✅ 「とりあえず書けた!」という成功体験が次の一歩を後押しする
✅ 「型を学べば、さらに良くなる」という実感が生まれる
「この調子で続ければ、慶應の小論文もいけるよ。」
「マジで? なんか、ちょっと書けそうな気がしてきた。」
「そうそう、その感覚が大事なんだよ。」
5. 次のステップ——「SFCの小論文の型」を学ぶ
「じゃあ次は、『SFCの小論文の型』を意識してみようか。」
SFCの小論文には、一般的な論説文とは異なる戦略が必要だった。
✅ 問題1つひとつを考えて解くのではなく、問題全体を見渡す
✅ 「最後の問4を書きやすくするために、問2をどう考えるか」など、全体の流れを意識する
✅ 知っていることや考えをただ書くのではなく、読み手に対していかに分かりやすく伝えるかが重要
✅ 読み手目線で書くことを意識する
「問題全部を目に通した上で、一問ずつ何を書くかを考えることが大事。」
「なるほど……じゃあ、最初から順番に書くんじゃなくて、最終的に問4をどう書くかを考えておいたほうがいいってこと?」
「そう! その視点を持つと、問1や問2の書き方も変わってくるよ。」
「確かに、それなら繋がりができるかも。」
彼は、試行錯誤しながら、全体の構成を考えるようになった。
6. 小論文が「戦える科目」に変わる瞬間
✅ 「とにかく書いてみること」の大切さを実感
✅ 「書きながら考える」ことで、論理的に整理できるようになる
✅ 「知識を増やすことで、文章の質が変わる」ことを理解
✅ 「読み手目線」を意識することで、より分かりやすい文章になる
「前より、だいぶ楽に書けるようになった気がする。」
彼の表情には、少しだけ「やれるかも」という自信 が芽生えていた。
私は、その変化を見逃さなかった。
(この調子で続ければ、いける。)
そして、この頃から彼の 「慶應経済も狙いたい」という気持ち が芽生え始める——。
📌 次回予告:第14話「受験生の冬」
 第14話「受験生の冬」
第14話「受験生の冬」